もくじ
日本画で欠かせない「ドーサ」について知ろう!

日本画で使われる「ドーサ」ですが、
どんなものなのかご存知ですか?
実は和紙にも使われていることが多く、日本画を描く上でも大切なものの一つです。
縁の下の力持ちのような存在ですね。
ドーサの基本知識を知っていると、和紙を選ぶときにも役立ちます!
今回は「ドーサ」について詳しく説明していきます。
ドーサとは何か?
ドーサは、漢字で「礬水」と書きます。
なにでできているかというと
・膠液(にかわえき)
・明礬(みょうばん)
この二つからできています。
ドーサを使うときは「ドーサを引く」と言います。
和紙にドーサを引くことで滲みどめの効果と、岩絵具や金、銀箔等の定着をさせることができます。
生和紙とドーサ引きの違いは?
ドーサが和紙に使われている場合には
和紙の種類に加えて「ドーサ引き」と書かれていることが多いです。
もう一つ「生」と記載のある和紙もあります。
ここでは、この二つの違いを解説していきます。
和紙-ドーサ引き-
和紙自体にすでにドーサが引いてあるもののことを指します。
この記載がある和紙は自分でドーサ引きをしなくても滲むことなくそのまま使用ができます。
場合によっては滲みどめが甘く、滲んでしまうこともあるので
使う前に試し書きすることをおすすめします。
和紙-生-
この記載がある和紙は 滲みどめの加工がされない状態=生 ということです。
つまり、自分で滲みどめ加工(ドーサ引き)をする必要があります。
ドーサ引きをしていない生の和紙は、このままだとにじむ状態です。
ドーサの作り方
ドーサは、自分でも簡単に作ることができます。
上にも紹介したように、ドーサの成分は膠液と明礬(ミョウバン)です。
実は、自分で作ることができます。
頻繁に使う方や、大量に使う場合には自作したほうが安く済みます。
一つ注意点は、ミョウバンは滲みどめの役割をしてくれる反面
濃度が濃すぎると作品の劣化につながる事があります。
適量を使用して、作品の劣化を早めることのないように注意しましょう。
ドーサ作りに必要なもの
・膠(三千本膠一本(約10g)/粒膠12〜15g) 膠の種類について詳しく知りたい方はこちら
・生明礬キミョウバン (約4.5〜5g)
・水(1L)
・乳鉢
・計量カップ
・できたドーサ液を入れる容器(蓋のできる小さめの瓶など)
・大さじ
・ボウル
ドーサ作りの手順
手順1. 膠水を作ります。
膠水の作り方は、膠を水に浸してふやけるまで待ちます。
水に浸すときの器は耐熱容器がおすすめです。
(この後の工程で湯煎をするため)
5時間ほどを目安にふやけ具合を見てみてください。
この待ち時間の間に手順2のミョウバンを加工しておくとスムーズです。
・三千本膠はタオルに包んでからハンマーなどで砕いて細かくしてください。
・粒膠はそのまま水につければ大丈夫です。
膠水のもっと詳しい作り方が知りたい方はこちら
手順2. 生ミョウバンを乳鉢で細かくします。
目安は触ってみてざらつきを感じなければOKです。
手順3. 膠を湯煎します。
湯煎なので、通常の家庭のコンロと、鍋があればできます。
膠が溶け切るまで、沸騰しないように注意しながら
たまにかき混ぜつつ様子をみます。
膠が溶けたら指で温度の確認をします。
火を止める温度の目安は、
指で一瞬触れられるくらいの温度です。このくらいになったら火を止めます。
手順4. 手順2の生ミョウバンを加えます。
少し混ぜ、生ミョウバンをなじませます。
手順5.ドーサ液の完成です。
使う時の注意点としては、気温が高い時はきちんと冷ましてから
気温が低い時は温かいまま使います。
保存について
自分で作ったドーサは長期保存が難しく、
作ったその日に使い切ってしまう方が良いのですが
その日に使い切るけれど1時間以上作業を中断するというときは
必ず冷蔵庫に保存してください。
出来合いのドーサ液を使う時も、一度出したものは元に戻さず
出したその日に使い切ることをおすすめします。
ドーサ液を購入できる場所と種類
ドーサ液は、作らなくても買うことができます。
日本画画材を扱っていれば取り扱いがあります。実店舗では種類が限られる場合があります。
参考までにアマゾンと世界堂通販をご紹介します。
ドーサの使い方
ドーサの使い方を解説していきます。
今回は、和紙に滲みどめ加工をする方法を解説します。
和紙をパネルに貼る前を想定しています。
そのため表と裏を2度塗りする工程をご紹介します。
パネルに貼った後でもドーサを引くことはできますし、
一度塗るだけでも滲みどめの効果は出ますので、お好みで使い分けをしてください。
必要なものは
・ドーサ液(ドーサ液が濃い場合は薄めたものを用意します。)
・ドーサ刷毛(ドーサ引き専用の刷毛、または彩色などに使っていないもの)
・滲みどめ加工をしたい和紙
・重し(文鎮やペットボトルなど)
・汚れても良いタオルや、大きめの下敷きなど
手順1
汚れても良いタオルや、大きめの下敷きを作業台に敷いて、
その上に和紙をおき、重しで和紙が丸まったり動かないように固定します。
手順2
ドーサ液を引いていきます。
きちんとドーサ液に浸して、軽く刷毛をしごいてボタボタ垂れないように注意してください。
手順3
ゆっくりと端から端まで刷毛を動かしていきます。
和紙がドーサ液を吸ってくれますが、吸いきれないと水溜りのようになり
綺麗な仕上がりにならないので水たまりができないように注意してください。
手順4
どんどん進めていきますが、必ず前に塗った部分と少し重なるように塗ってください。
塗り残しがないよう、ゆっくりと、確実に作業をしてください。
手順5
全て終えたら、一度乾燥させます。
きちんと乾燥ができたら、裏面も同じようにドーサを引いていきます。
2度目は和紙の吸水力が1度目ほどはありません。
そのため水たまりができやすくなるので一層注意しましょう。
全て終えて乾燥させたら完成です。
乾燥するとドーサがきちんと引けている証拠として
和紙の表面がキラキラとします。
きちんと引けたかの目安として確認してみてください。
まとめ
ドーサは、膠水と明礬から出来ていて
滲みどめや岩絵具の定着をさせる役割があります。
ドーサは作ることもでき、画材店で購入することもできます。
ドーサを作る際に必要なものは、
今回紹介するために使ったものがこちら
- 膠(三千本膠一本(約10g)/粒膠12〜15g) 膠の種類について詳しく知りたい方はこちら
- 生明礬キミョウバン (約4.5〜5g)
- 水(1L)
- 乳鉢
- 計量カップ
- できたドーサ液を入れる容器(蓋のできる小さめの瓶など)
- 大さじ
- ボウル
分量の計算をしやすくするためにまとめると
水1Lに対する生ミョウバンは約4.5〜5g、膠は11〜12gです。
また、ドーサを引くときはゆっくりと染み込ませるように引くことと、
ドーサ液をたっぷりつけすぎず、水たまりができないようにすることに注意してください。
ドーサ液を作るのは少し面倒ですが、大きな紙に引くときなどは
作ってしまった方が安くできるのでおすすめです。
少量でも、分量などを変えれば使い切れる量が作れます。
ドーサ引きされていない和紙も絵を描けるように加工できるので便利です。
ドーサ引き、ぜひ試してみてくださいね。
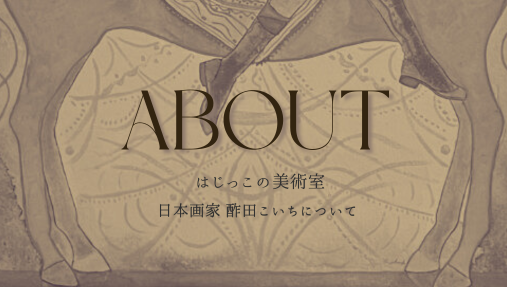
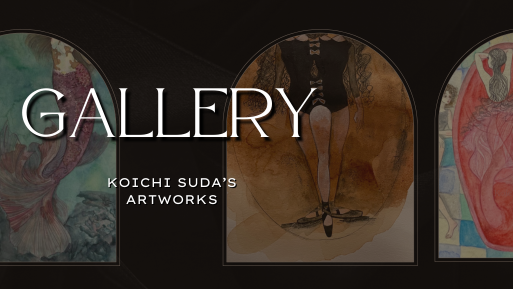

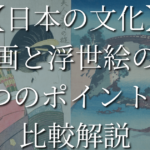

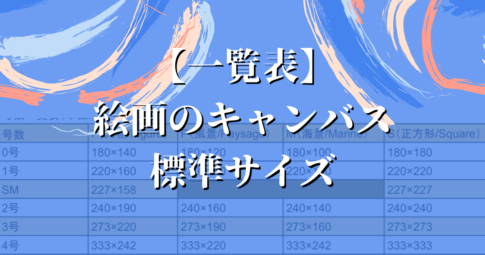
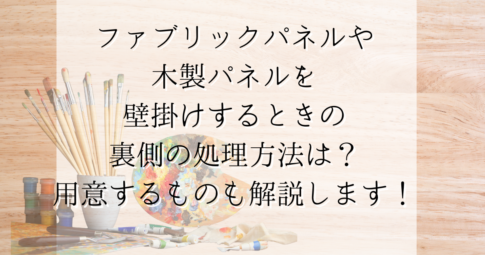




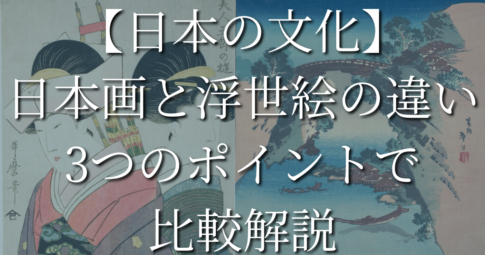



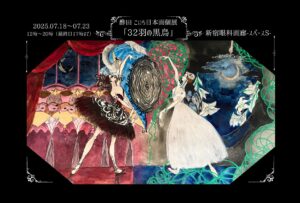

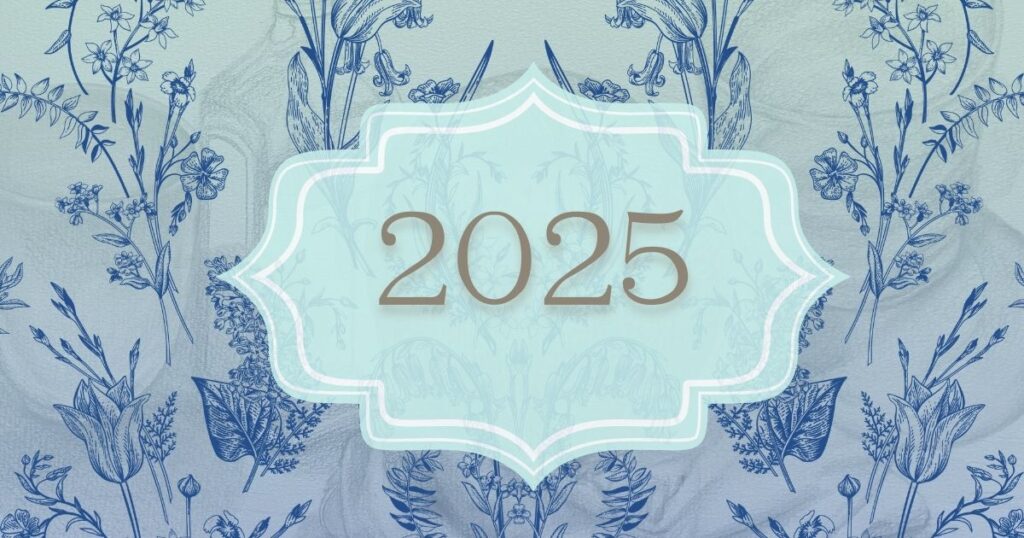
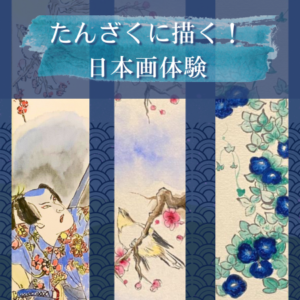



コメントを残す