もくじ
日本画には欠かせない膠について学ぼう!
日本画で制作をする上で欠かせない膠(にかわ)。
今回は、膠を含めた日本画の歴史を簡単におさらいし、
おすすめの膠、選び方から簡単な使い方まで解説していきます。
日本画の基礎知識
日本画についてより詳しく知りたい方はこちら
日本の絵画について
絵を描くことそれ自体は、縄文時代から始まります。
平安時代には中国の絵画技法が導入されたことにより新しい画風が生まれました。
鎌倉時代には禅画や南宋画の影響を受けた山水画が盛んに、町人画や南蛮屏風など、さまざまな画風が生まれました。
江戸時代では浮世絵が生まれ歌舞伎や芝居のシーンなどを描いた木版画が流行しました。
また、染色技術を加えた屏風や襖絵、屋内装飾画なども発展しました。
明治時代には、開国したために西洋の絵画が流入したため日本国内の絵画との違いを示すため
日本国内のさまざまな流派などを全てまとめて「日本画」という言葉が生まれました。
現代では古典的な技法や画風とともに
新しいアイデアや表現方法を取り入れた作品が多く生まれています。
また、皮や人工的な素材や新しく生まれた技術を使った美術活動も行われています。
日本独自の絵画は、歴史と文化的背景によって独特の表現方法や美の基準を持っています。
膠をはじめとした伝統的な材料や技法を使用することで、
日本画の歴史や伝統を感じる作品を制作することができます。
膠の役割と使い方
膠の種類と特徴 〜原料の違い〜
膠は、動物の皮膚や骨から抽出される、天然の接着剤です。
日本画などの伝統的な工芸品や修復技術など、様々な分野で利用されています。
代表的な膠の種類としては、豚皮膠や魚膠、獣膠などがあります。
それぞれの膠には特徴があり、用途に合わせて選ぶことが大切です。
勾玉膠(こうぎょくごう)/豚皮膠
豚皮膠は、一般的に多く利用される膠の一つです。
柔軟性があり、耐久性が高い特徴があります。
主に金箔や彩色の際に使用されます。
また、優れた接着力を持ち、紙や布などの材料にも適しています。
注意点としては、湿気に弱いため保存が難しい場合があります。
魚膠(ぎょこう)
魚膠は、透明度が高く、独特の光沢感を持っています。
水に溶けやすく、下地の下塗りや染料を使った彩色に使用されることが多いです。
食品のゼリーやパフェなどにも利用されることがあります。
注意点としては
豚皮膠に比べると弾力性が低いため、細かな作業には向いていません。
米膠(べいこう)
米を原料として作られる植物性の膠です。
魚膠よりも粘度が高く、柔らかい質感があります。
また、紙や絹の補強や裏打ちに使用されることが多く、
保水性があるため絵具の乾燥を遅らせる効果もあります。
獣膠
獣膠は、柿渋と混ぜ合わせて使用することが多いです。
耐久性が高く、風合いのある仕上がりが得られます。
また、耐水性があり、木材や漆器の修復にも利用されます。
膠は天然素材ということをしっかりと覚えておきましょう。
そのため湿度や温度の変化によって品質が変化することがあります。
取り扱いには注意をし、保管の際には密閉容器に入れて湿気を避けるようにしましょう。
また、膠を溶かす際には、温度や濃度などの条件を正確に調整し、沸騰させないようにすることが大切です。
膠の形状と選び方
基本的な膠の種類がわかったところで、では何を買えばいいのか?
原材料も特徴も少しずつ違う膠を、一体どんなふうに選んだらいいのか
迷ってしまう方も多いと思います。
膠は、さまざまな形になって販売されています。
ここからは、形状と用途別に膠を紹介していきます。
これを確認しながら膠を選んでいくと
自分の作品制作に合ったものが見つかると思います!
1.膠液
形状:液体状で、瓶などに入っている膠です。
販売状況や気温などによってゼリー状に固まっているものもあります。
使う時に溶かせば問題ありません。
以下で詳しく解説していきます
使い方:
・中身が液体のままの場合
中身が液体のまま保存できている場合には、
そのまま必要な分を出してまず岩絵具と混ぜてよく練り、
その後水と混ぜ適度に薄めます。
・中身がゼリー状に固まっている場合
瓶に入っているものが多いので、瓶ごとお湯に入れて溶かすことができます。
もしくは、中身をスプーンなどで使う分だけすくって絵皿などにうつし、温めて液状に戻す方法です。
その後は上記と同じで、岩絵具と膠液を混ぜてから水を加えて使います。
2.強靭膠液
通常の膠液との違い:濃度が違います。強靭膠液の方が数倍濃く作られているので、
通常の膠液よりも定着力が強く、粗い岩絵具などを定着させる場合におすすめです。
形状:基本は液体状で、通常の膠液と同じように温度によって固まっている場合があります。
使い方:使い方は通常の膠液と変わりません。
・中身が液体のままの場合
中身が液体のまま保存できている場合には、
そのまま必要な分を出してまず岩絵具と混ぜてよく練り、
その後水と混ぜ適度に薄めます。
・中身がゼリー状に固まっている場合
瓶に入っているものが多いので、瓶ごとお湯に入れて溶かすことができます。
もしくは、中身をスプーンなどで使う分だけすくって絵皿などにうつし、
温めて液状に戻す方法があります。
その後は上記と同じで、岩絵具と膠液を混ぜてから水を加えて使います。
3.粒膠
形状:小さな石ころ状
使い方:必要な分をとり、ふやかした後に溶かして
岩絵具と練り混ぜて、水を加えて使います。
ふやかす際の水の分量は以下を参考にしてみてください。
(例)水50mlに膠を5g入れ、ふやかした後溶かして使います。
三千本膠
形状:膠を固め、棒状に乾燥させたものです。
名前の由来は昔の単位の1俵にこの膠が約三千本入っていたからだと言われています。
形状は細長く、べっこう飴のような色艶をしていて、非常に硬いです。
使い方:水につけてふやかし、湯煎で溶かす。
その後ガーゼで漉して液状の膠として使えます。以下で詳しく説明します。
三千本膠の使い方
三千本膠を砕く
適度に細かく砕きます。砕く際は手でも折ることができますが、
必ず手袋をしたり、タオルなどで包んで破片が手に触れないようにしてください。
ハンマー等で砕く場合も飛び散りを防止するためタオルで包んでください。

ふやかして柔らかくする
砕いた膠10gに対し60ccから100ccほどの水を用意します。
膠全体が水につかるのがベストです。

膠を水に半日ほどつけておきます。
水を吸って柔らかくなった膠にかたい芯がなく、ぷるぷるとゼリーのようになっていればOKです。
水が残った場合は、少量であればそのまま次の過程へ進みます。
あまりに水が多く残ってしまった場合は捨ててください。
少し深めのお皿に膠をセットして次の工程に進みます。
湯せんで溶かす
お湯を用意し、沸騰しないように温度に注意しながら湯せんで溶かします。
「湯せんセット画像」
ガスやIHで湯せんをしていると膠が焦げる場合があります。
焦がさないように掻き回しながら弱火で行ってください。
少し独特の臭いがありますので、換気をすることをおすすめします。
膠がとろとろの液体状になればOKです。
溶けた膠をこす
溶けた膠をガーゼを使ってをこします。
こすことで岩絵具と混ぜた時の発色が良くなります。
保存がしやすい瓶などの容器、または少し深めのお皿を用意します。
画像は参考までに、空いたジャム瓶を使って漉すセットを用意しているところです。

このように
容器にガーゼをセットし、膠を流し込みます。

最後にガーゼに残った膠をギュッとしぼって完成です。
使ったガーゼはにおい対策をして生ごみや、
燃えるゴミとして捨てる事をおすすめします。
完成
完成したら、
すぐに使う場合は適量をまず岩絵具と混ぜて練り
その後に水を混ぜて使用してください。
すぐに使わない場合でもできるだけ早く使い切り、
必ず冷蔵庫などの涼しい場所に保管してください。

保管容器はジャムの瓶やお皿などなんでも良いです。
お皿などの蓋がついていない容器の場合は必ずラップなどでふたをしましょう。
余計なホコリが入るのを防ぎ、においが出ないようにするためです。
常温や温かいまま放置すると腐ってしまうので必ず冷蔵庫などで保管してください。
保管した膠の使い方
冷蔵庫などで冷えた膠はゼリーのように固まりますが、
温め直せば液体状になります。
温め直すための方法は電気保温トレイ、マグカップウォーマーなどに乗せておく
これが一番楽に溶けてくれます。
保温トレイなどがなければ
冷えた状態の時に使う分を別の絵皿にとって移して
移した方にラップをして10秒ほど電子レンジで温める方法もあります。
ただしこれはかなり無理矢理なので焦げができる場合があり、
もしやるのであればしっかり電子レンジを見張ってください。
オーブンではできないので絶対に試さないでください。
異臭と掃除で大変なことになります。
膠を使う際の注意点
・膠が乾燥すると硬化してしまうため、塗る面積が広い場合には、途中で水で濡らしておくことが大切です。
・膠が乾燥すると、膠膜が剥がれてしまうことがあるため、環境温度や湿度に注意して作業を行いましょう。
・温度が低い場合には簡単に固まってしまうため、作業場所の温度にも注意が必要です。
三千本膠の保存方法(乾燥した状態)
・乾燥した状態の膠は湿度が高い場所で保管するとカビが生えやすく、
劣化が早くなることがあります。乾燥した場所に保管するようにしましょう。
このように膠は天然素材であるため使い方や取り扱いには注意が必要ですが、
私が膠を保存するときにおすすめしているのは
お菓子などに入っている乾燥剤などを一緒に入れておくことです。
乾燥剤だけ売っているので新しく買った方が乾燥力も持続します。
膠は保存の際は湿気に弱いので、
乾燥剤を入れて暗所で保管しておけばそこまで劣化せず保存が可能です。
ただ、長らく保管していると少しずつでも劣化は必ずしますので
できるだけ良い状態で使うことをおすすめします。
三千本膠の保存方法(膠液にした状態)
使えるように膠液に加工したものは長期の保存はできません。
冷蔵庫などの温度が均一の場所、冷暗所に保管し、
約1週間を目安になるべく早く使い切ってください。
放置してしまうとにおいが強くなり、接着力も低下しますので注意してくださいね!
膠を取り扱っている場所は?店舗と通販のおすすめ
ここでは、膠を購入できるおすすめの実店舗やネット通販をご紹介していきます
実店舗
実店舗のメリットは実際にものを見て購入することができる点です。
関西:
カワチ画材
http://www.kawachigazai.co.jp/store.html
画箋堂
http://www.gwasendo.com/company/products.html
関東:世界堂
https://www.sekaido.co.jp
関東にチェーン展開しています。
通販もかなり充実していて、日本画画材のオンライン限定のセットなども販売しています。
通販を使う際にはあまり急がない場合におすすめです。
膠で糊の代わりに使うことができる!
昔から接着剤として使われてきた膠のもう一つの使い方
膠の粘性を生かした糊代わりの使い方
膠は古くから糊代わりに使用されてきた接着剤です。
特に昔ながらの方法で木材や、紙を接着したいという方には向いています。
しかし、その粘性を生かした使い方についてはあまり知られていません。
そこで今回は膠の粘性を生かした糊代わりの使い方について紹介します。
膠を糊代わりに使用する場合は、
通常の糊と同様に水に溶かして使用します。
ここでの注意点は
膠は水に溶かすと
温度によっては溶けたままでは固まりにくくなるということです。
溶かした後は保温する必要があるので、特に冬場は注意が必要です。
保温のためのグッズとしては、マグカップウォーマーなどがおすすめです。
日本画用のものでなくても便利に使用できます。
次に、膠を糊代わりに使用する際のポイントは
接着面に塗布する前に十分に乾かすことが重要です。
膠は乾燥すると強い接着力を発揮します。
接着力が弱くなる可能性がある条件がいくつかあります。
- 接着面が湿っている
- 膠は接着面が汚れている(接着面は事前に清掃しておきましょう)
さらに、膠を使用する場合は、
接着面の形状や材質に合わせて適切な膠を選ぶ必要があります。
例えば木材の場合は、鹿膠が適していますし、
紙などの薄い素材の場合は、アイスランド膠や魚膠が適しています。
このように膠を糊代わりに使用する際には、
溶かし方や乾かし方、選び方に注意する必要があります。
正しく使うことで、膠の持つ粘性を生かした強い接着力を発揮させることができます。
昔ながらののりづけの体験は難しい部分もありますが、
日本画の歴史を体験として学べるので
興味がある方はぜひ挑戦してみてください。
膠を使った日本画の制作方法の流れ
膠は、昔から日本画の制作をする上で欠かせない材料であり、
糊や顔料として使われてきました。
膠は、魚の皮や骨から作られる天然素材で、水に溶けやすく
乾燥後も強力な粘着力を持ちます。
そのため、膠を絵の具に混ぜたり、描いた後に表面に塗ることで、
色の定着力を高めたり、作品の耐久性を向上させることができます。
日本画で膠を使う際の、基本的な技法の流れ
下地の作成
紙を下地として使う場合は、
紙を張るか裏打ちをして、湿度の影響を受けずに作品を作れるようにします。
また、下地には通常滲みどめを施します。
膠と顔料の混合
膠と顔料を混ぜて、色を調合します。この際、膠を十分に溶かしてから顔料を混ぜることで、より均一な色を出すことができます。
線描き
顔料を混ぜた膠を紙に塗布してから、
面相筆など、線描きに適した細かい筆で線を描いていきます。
線は、状況に応じて細くしたり太くしたりなど
描く力を調整することで、表現の幅を広げることができます。
あまり力を入れないことがポイントです。
塗り
線描きの後は、膠と顔料を混ぜたものを筆で塗っていきます。
塗りは彩色筆など、適した筆を選ぶことで
深みのある色合いを表現することができます。
この流れが、膠を使った日本画の基本的な技法です。
日本画を始めたい方むけに
こちらではより詳しく解説していますのでもっとよく知りたい方におすすめです
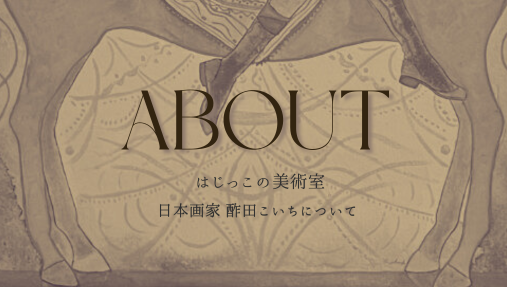
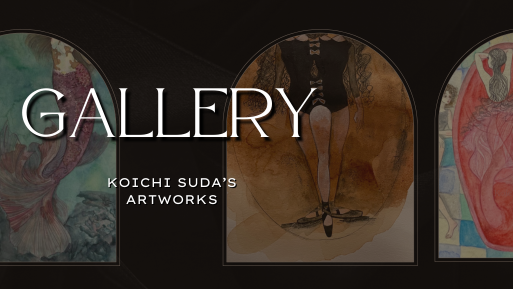
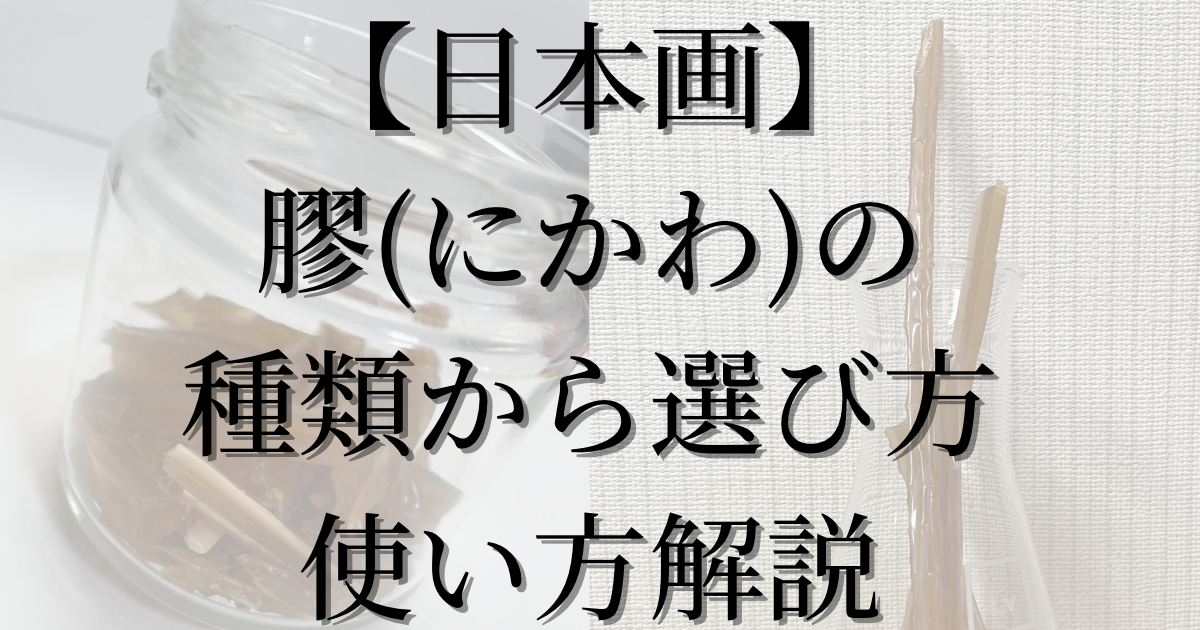



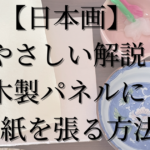
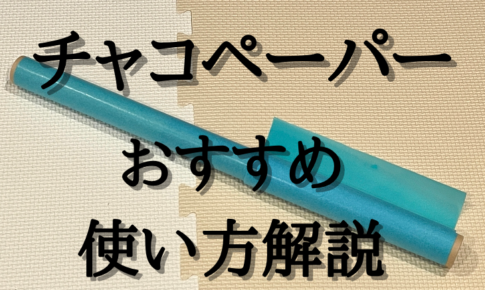
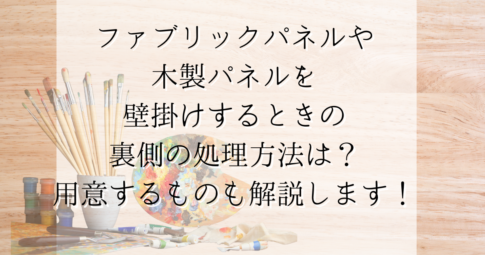



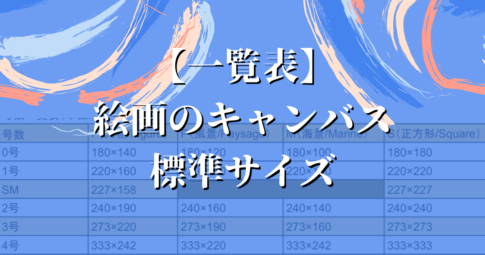
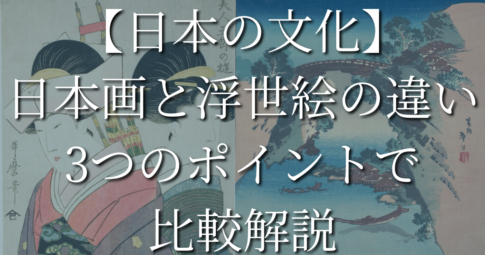


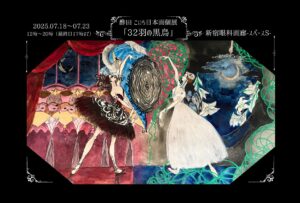

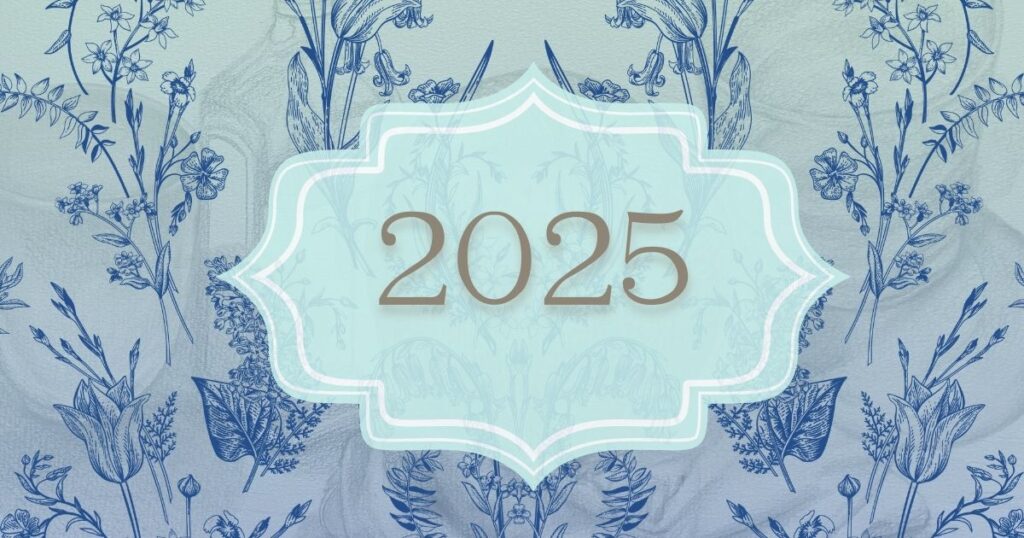
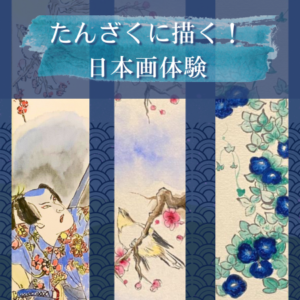



コメントを残す